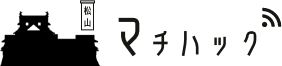令和7年(2025年)11月2日(日)~11月3日(月)の2日間、愛媛県大洲市で開催される「大洲まつり」は、300年以上の歴史を誇る伝統行事です。
最大の見どころは、江戸時代の参勤交代を再現した壮大な行列「お成り」。約260名もの参加者が装束をまとい、大洲市内を練り歩く姿は圧巻です。さらに、子供みこしパレードや郷土芸能の披露、地元グルメが楽しめる屋台など、家族で一日中楽しめるイベントが盛りだくさん。
本記事では、大洲まつりの日程と見どころを詳しくご紹介します。
2025年 大洲まつりの日程

開催時期と場所
大洲まつりは毎年 11月2日(日)~11月3日(月) にかけて、愛媛県大洲市で開催されます。
メイン会場は大洲藩総鎮守とされる 八幡神社 を中心に、市街地全体が祭り一色に染まります。秋の深まりとともに開催されるため、紅葉と祭りの雰囲気を同時に楽しむことができるのも魅力です。
| イベント名 | 会場 |
| お成り | 八幡神社→市内→八幡神社 |
| 大洲まつり | 中村地区緑地公園(肱川緑地) |
お問い合わせ先:大洲商工会議所
八幡神社との関わり
大洲まつりの中心にあるのが、 大洲藩総鎮守の八幡神社 です。御神幸祭(お成り)は、御祭神の御神霊を3基の鳳輦に遷し、市内を巡行する神事として受け継がれてきました。
江戸時代から続くこの行事は、大洲市指定の無形民俗文化財に登録されており、地域の人々にとって欠かせない伝統文化となっています。
大洲まつり最大の見どころ「お成り」
お成りとは?その歴史と由来
「お成り」とは、大洲藩時代から続く伝統的な神事で、江戸時代中期から300年以上の歴史を持ちます。
御祭神が3基の鳳輦(ほうれん:お神輿)に遷り、装束をまとったお供に護られながら市内を巡幸する行列です。藩政時代には約600名が参加して行われ、藩主から神馬3頭が供奉されたこともあり、格式と豪華さで知られています。
現代でもその伝統を守り、地域の有志や小中学生が参加しています。
江戸時代から続く大名行列「八八の供」
お成りの行列の先頭を務める御長柄組(槍を持った隊列)は、「八八の供」と呼ばれる独特の歩調で進みます。この歩調は、大洲藩の参勤交代時に整えられたもので、太鼓のリズムに合わせた美しい動きが特徴です。
「八八の供」とは、行列の供の一部が八人ずつに編成されていたことに由来し、江戸城入場の際にもその歩調が評価されました。
豪華な行列の構成と参加者
行列には約260名が参加し、御神輿を中心に「御先払い」としてほうきで道を掃く役や、長柄やりを持った侍役などが続きます。
かつては約600名(御長柄組120組、鉄砲組60挺)が行列の先駆を務め、華やかな神馬3頭も加わっていました。現在でもその伝統を受け継ぎ、衣装や道具が整えられ、地域の子どもや有志が列に加わります。
巡行ルートと距離
お成りの巡行は八幡神社を出発し、大洲市内を約7~12キロにわたり練り歩きます。途中、2ヵ所の御旅所では巫女による鈴神楽や浦安の舞が奉納され、町中に雅楽の音色と行列の迫力が広がります。
市街地を巡るこの壮大な行列は、全国的にも非常に珍しい光景として多くの見物客を魅了しています。
2日目のお楽しみイベント
おまつり村と郷土芸能ステージ
大洲まつりの2日目は、おまつり村広場を中心にさまざまな催しが行われます。
地元の郷土芸能が披露されるステージでは、太鼓や舞踊、民謡などを一日中楽しむことができ、地元文化に触れる貴重な機会です。観覧するだけでなく、参加型の体験コーナーもあり、大人から子どもまで楽しめます。
子供みこしパレード
子供たちが元気に練り歩く「子供みこしパレード」は、家族連れに大人気のイベントです。
小さなお神輿を担ぎながら、笑顔あふれる行列が街中を練り歩き、観客と一体となったお祭りの雰囲気を楽しめます。子どもたちの元気な姿は、祭り全体に活気を与えています。
屋台グルメと地元の味覚
祭りの醍醐味といえば、屋台で味わえるグルメも見逃せません。地元の食材を使った郷土料理や定番の屋台メニューが並び、食欲の秋を満喫できます。
友人や家族とシェアしながら、祭りの雰囲気を楽しむことができるほか、地元の特産品や手作りお菓子も手に入れることができます。
文化財としてのお成り
大洲市指定無形民俗文化財の価値
大洲まつりで行われる「お成り」は、江戸時代中期から続く歴史ある神事で、約300年以上の伝統を誇ります。その長い歴史と独自の行列形式が評価され、大洲市では「八幡神社の祭礼行事とお成り」として無形民俗文化財に指定されています。
行列の先頭を務める御長柄組の歩調「八八の供」など、昔ながらの儀礼や美しい動きは、現代でも見ることができる貴重な文化遺産です。
行列で使用される貴重な神具と衣装
お成りの行列には、装束をまとった約260名の参加者が、槍や長柄、鳳輦(ほうれん:お神輿)を携えて練り歩きます。
中には江戸時代から使用されている神具や、1700年代半ばに作られた「楯」などもあり、長い歴史を感じさせます。
また、装束や神輿の装飾は、当時の大洲藩の格式を伝える貴重な資料として保存され、伝統の美しさを今に伝えています。
復活した「道楽」と雅楽演奏
近年では、江戸時代まで行われていた「道楽(みちがく)」が復活しました。これは行列の中で雅楽演奏者が歩きながら演奏を行うもので、大洲の町並みを悠久の音色が彩ります。
鵜飼いシーズンには、船上での演奏も行われ、行列と雅楽の融合による独特の雰囲気を体験できます。
この伝統を守るため、地元の有志による参加者募集も行われており、地域文化の継承に大きく貢献しています。
お成りを守り続ける取り組み

御神幸保存会の設立と活動
「お成り」は300年以上続く大洲市の伝統行事ですが、奉仕者の減少や多額の費用がかかることから、開催の継続が難しい時期もありました。
こうした状況を受け、平成2年に「御神幸保存会」が設立され、伝統行事の保存と継承を目的とした活動が始まりました。
設立当初には約1,100名の方々が参加し、衣装や道具の整備、行列運営の支援など、祭りの維持に欠かせない役割を担っています。
続けていくための課題と支援の呼びかけ
現在も「お成り」を完全に守り続けるには、多くの課題が残っています。修復が必要な神具や新調が求められる衣装など、費用面や人手の確保が大きな課題です。
そのため、祭りを支える活動への協力や支援を呼びかけています。地元住民だけでなく、伝統文化に関心のある方も参加できる形で支援が可能です。
会員特典と参加の方法
御神幸保存会に加入すると、会員として祭りの支援に参加できるほか、様々な特典があります。
| 会費 | 1口 2,000円(1年間) |
| 申込方法 | メールまたはお電話 |
- 御神符(お守り札):毎秋に祈念された御神符を授与
- お屠蘇:新年を迎えるための特別なお屠蘇を受け取れる
- 家内安全祈願:年始に家族の安全を祈願
参加申し込みリンクはこちら
まとめ
大洲まつりは、300年以上の歴史を持つ大洲市の伝統行事で、江戸時代の参勤交代を再現した「お成り」が最大の見どころです。
装束をまとった約260名が市内を練り歩く壮麗な行列は圧巻で、八幡神社を中心に巡行する姿は地域の誇りでもあります。さらに、子供みこしパレードや郷土芸能の披露、屋台での地元グルメも楽しめ、家族や友人と一日中満喫できます。
歴史と文化、食と楽しみが融合した大洲まつりは、観覧スポットや写真映えのポイントを押さえることで、より深く魅力を体感できます。